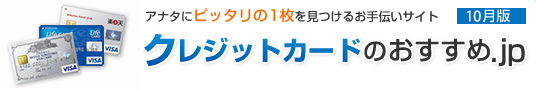
クレジットカードの歴史
世界中で当たり前のように使われているクレジットカード。
しかし、現在のようにカード1枚だけで国内外の決済に利用できるようになったのは、実はここ30年あまりのことなのです。いったいどのような過程を経てクレジットカードは進化してきたのでしょうか。
三菱UFJニコスが東京・秋葉原の本社に常設しているカードギャラリーを参考に、クレジットカードの歴史を振り返ってみましょう。
クレジットカードの起源はクーポン券
クレジットカードと言えば、プラスチック製のカードを思い浮かべる人がほとんどだと思いますが、実は最初から「カード」だったわけではありません。
日本におけるクレジットカードの起源と言われるのが、1951年に日本信用販売(後の日本信販、現在は三菱UFJニコス)が開始したクーポン券を使った割賦購入あっせん事業です。その少し前からもチケットを使った分割払い制度が開始されていましたが、日本信用販売は1冊に500円券が2枚、100円券が14枚綴りになったクーポン券を考案しました。当初は高島屋、松屋、京浜百貨店、白木屋の4百貨店で利用でき、支払いは後日給与から天引きされる制度となっていました。
その後、各地で相次いで信用販売会社が設立され、1960年に丸井が紙製クレジットカード、ビニール製カードを発行。そして1961年に日本ダイナースクラブがプラスチック製のカードを発行し、名実ともにクレジットカードとなりました。
相次ぐカード会社の設立
1959年、信用販売制度に大きな影響を与えるような出来事が起きました。
通商「34年通達」と呼ばれるもので、通産省(現経済産業省)からの通達により、一定金額以下の商品やサービス、食料品などに対してのクーポン券の利用禁止、クーポン券の発行にも地域制限がかかるといったもので、これにより、日本信販は大阪・名古屋の両拠点を撤収し、各拠点の設備や営業権を大阪信用販売(現アプラス)と中部日本信用販売(後のセントラルファイナンス、現時はセディナ)に譲渡しました。
なお、この34年通達は1992年まで継続されました。
60年代後半になると、都市銀行が相次いでクレジットカード事業に参入していきました。
三菱銀行系のダイヤモンドクレジット(DC、現在は三菱UFJニコス)、住友銀行系の住友クレジットサービス(現三井住友カード)、東海銀行系のミリオンカード(MC、後のUFJカード、現在は三菱UFJニコス)、第一・日本勧業・富士・太陽・埼玉などの各銀行が資本参加したユニオンクレジット(原則固定UCカード)などが設立されました。
1961年に設立されたJCBも、実は三和銀行と日本信販の折半出資によるカード会社で、日本信販は「クレジット業界のパイオニア」と呼ばれることもあります。
国内外共通カードの発行
海外でのクレジットカードの利用が始まったのは1963年のこと。当時はまだ渡航外資規制があり、海外だけで使える有効期限付きの渡航者専用カードは別発行でした。
同一のカードが国内外共通で利用できるようになったのは1978年。
日本ダイナースクラブの「インターナショナル・カード」を皮切りに、1980年には住友クレジット(現三井住友カード)が国内外共通のVISAカードを発行。その後、DC、MC、UCも国内外共通のマスターカードを発行し、JCBは独自に加盟店開拓を進め、アメリカン・エキスプレスは日本支社を設立しました。
1986年に日本信販がビザ・インターナショナルからVISAカード発行権を得ると、VISAカード、マスターカードの両国際ブランドの並行発行が開始され、以降は他社でも国際ブランドの並行発行が定着しました。
これにより、多くのカード会社で、VISA、マスターカード、JCBなどの国際ブランドをユーザー自身が選べるようになりました。
多様な企業の参入
1970年代から1980年代前半は、カード業務代行の全盛期となりました。
小売り・サービス業にとって、クレジットカードは有力な販促手段となっていましたが、カード発行のノウハウや信用供与に乏しい業者は、カードの発行を信販会社に業務委託するケースが急増し、提携企業も百貨店やスーパーだけでなく、多方面に広がっていきました。
また、80年前後には流通系カードと呼ばれる会社の設立も相次ぎました。
1982年に改正銀行法が施行され、クレジットカード業務が銀行の付随業務として認められると、銀行はカード事業への取り組みを一段と強化し、銀行本体が発行する地銀カードが誕生したり、JCBやUCなどの参加銀行が独自にカード会社を設立するなど、銀行系カードのフランチャイズ展開が地方へも広がりました。
さらには銀行だけでなく、郵便局や生命保険、証券会社などの金融機関もカード事業に進出を始めました。
サービス強化と業界再編
1980年代からは、クレジットカードの決済機能が一通り整い、技術革新も相まって他社との差別化やサービスの強化が進んでいき、ポイントプログラムの導入や年会費無料、キャッシュカード機能との一体化、ゴールドカードの普及など、カードに付加価値をつける動きが目立つようになりました。
しかし、2000年代に入ると不況の影響もあり、企業体質の強化が加速。メガバンクの再編と共にカード業界の再編も進みました。
大きなところではMCとフィナンシャルワンカードが合併したUFJカードが、さらに日本信販と合併してUFJニコスとなり、その後協同クレジットカードサービスのDCが合併して2007年に三菱UFJニコスになりました。
現在では、電子マネーの本格普及、オンライン決済の増加などにより、公共料金も含め、カード払いが可能な場所が増え続け、日常生活におけるクレジットカードの重要性はますます大きくなっています。完全なキャッシュレス社会の到来もそう遠くはないのかもしれません。

楽天ポイントと普段使いのクレジットカードのポイントが二重で貯まるマル秘テクニック...

「楽天Edy」や「WAON」など、各種電子マネーについて解説しています。キャンペ...

ガソリンを安くお得に給油できるガソリンカードの上手な使い方をご紹介しています。...

クレジットカードにまつわるよくある質問をまとめました。みなさんの疑問にお答えしま...
